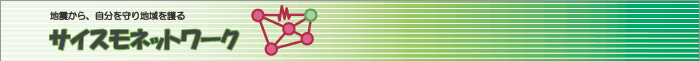緊急地震速報とは
地震観測網から得られた地震情報を即座に伝達し、住民の生命を守ることや社会経済に与える損害を軽減するための情報です。
地震波には伝播速度が速い「P波(初期微動)」と、伝播速度は遅いが大きな揺れを起こす振幅の大きい「S波(主要動)」があります。
地震による被害の大半はS波到着以降に引き起こされることから、地震発生直後に震源に近い観測点で得られた地震波データ(P波)をもとに、震源情報(震源地/発生時刻/地震の規模)を瞬時に推定し、S波が到着する前に自分のいる場所に「いつ」「どのくらい」の揺れがくるのか伝達する安全管理システムです。
ただし、ごく短時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度や猶予時間に誤差が生じたり、誤報を発報する可能性もあります。
また、能登半島地震のような直下地震や東海地震、東南海、南海地震のような連動型地震には対応できない点が問題視されています。
緊急地震速報を適切に活用するためには、このような特性や限界を十分に理解する必要があります。
緊急地震速報のしくみ
先に届く小さな揺れ「P波」を気象庁の地震計が検知し、被害を起こす大きな揺れ「S波」が到着する前に緊急地震速報でお知らせします。
※ダウンロードで上記動画のダウンロードができます。
緊急地震速報<直下地震>
直下地震の場合は緊急地震速報が間に合わないとされています。
※ダウンロードで上記動画のダウンロードができます。
緊急地震速報を入手すると・・・
緊急地震速報によって生じる時間は長くても数秒から数十秒です。
震源に近いところでは情報が間に合わないこともあります。
しかしたとえ数秒から十数秒でも早く、大きな地震を知ることができれば、被害を大きく減らす減災効果が見込めると言われています。
緊急地震速報を見聞きしたときは
緊急地震速報を見聞きしたときの行動は「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。
つまり、まずは自分の身の安全を守ることが第一となります。
緊急地震速報=減災?
緊急地震速報が導入されるだけで、それが即減災に繋がるのでしょうか?
答えは「ノー」です。
緊急地震速報が導入されるだけでは即減災には繋がりません。
事前の対策を行っていなければ、むしろ緊急地震速報を聞いた人たちが慌てて避難するなどのパニックにより被害が大きくなることも考えられます。
緊急地震速報を有効に活用するためには地震発生前の「事前対策」、緊急地震速報受信時の「対応行動」、地震発生後の「事後対応」、それらを事前に考え、緊急地震速報を見聞きしたときに適切な行動を取ることによって、初めてその効果が大きく発揮されます。
緊急地震速報導入初期においては、短期間で複数回の訓練実施を推奨します。
大地震が発生したら「防災に対する心構え」
大地震が発生した場合には「自助」「共助」「公助」を意識して下さい。
自助
「自らの安全は、自らが守る」
一見自分勝手な言葉に感じますが、防災では一番重要な事になります。
大きな地震の揺れの中では、誰もが自分の身を守ることしかできません。
自分が助かれば、多くの人を助けることができます。
自分が助かれば、火事の初期消火ができます。
こうした、「自らの安全は、自らが守る」という備えと行動を、「自助」と呼びます。
共助
「共に助け合う」
大地震が発生した場合、地域の防災機関(警察や消防など)が、同時にすべての現場に向かうことはできません。また自衛隊など被災地の外からの応援の到着には時間がかかります。
このとき、職場や地域の人たちと共同で助け合う事を「共助」と言います。
共同で助け合えば、患者さんを避難させることができます。
公助
警察・消防・都・国といった行政機関、ライフライン各社を始めとする公共企業、こうした機関の応急対策活動を、「公助」と呼びます。
緊急地震速報の運用概要
緊急地震速報の運用に付いては下記の図のように、地震発生前の「事前対策」、緊急地震速報受信時の「対応行動」、地震発生後の「事後対応」と大きく3つの項目に分けて運用を想定します。
|
|
|
|
 |
|
|
緊急地震速報 導入の流れ
防災対策委員会を作ろう
防災対策委員会を作ることによって、担当者が決まり、作業を分担することもできるので、導入・運用がスムーズに進みます。
緊急地震速報を入手しよう
緊急地震速報は、テレビ・ラジオ、緊急地震速報の放送に対応している防災業務無線・携帯電話、(財)気象業務支援センター、民間の情報配信会社から入手することができます。
緊急地震速報を導入するのであれば、専用端末等を利用して民間の情報配信会社から入手することになると思います。
緊急地震速報を提供する事業を行っている事業者は 「緊急地震速報利用者協議会」の「関連事業者の紹介」で知ることができます。機能や料金を比較して、事業者を選択しましょう。
緊急地震速報の説明会を開こう
緊急地震速報についてやその効果などを説明して、緊急地震速報導入を周知しましょう。
「ダウンロード」の「緊急地震速報 導入資料」はどなたでもダウンロードできます。ぜひご利用ください。
また、気象庁の「緊急地震速報の利活用の手引き(施設管理者用)Ver.1.0」
(http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/usage/index.htmlよりダウンロード可能)も大変参考になります。
転倒防止対策や、避難経路の策定・確保
転倒防止対策や、避難経路の策定・確保を行いましょう。
対応行動、事後対応マニュアルの作成と緊急地震速報を用いた避難訓練
対応行動、事後対応マニュアルの作成と緊急地震速報を用いた避難訓練を行います。
緊急地震速報導入初期においては、短期間で複数回の訓練実施を推奨します。
緊急地震速報を利活用する導入資料と運用マニュアル
サイスモネットワークでは、緊急地震速報を導入する際の資料や掲示物を「ダウンロード」にて公開しております。
この資料は営利目的でなければ、どなたでもダウンロードし利用することができます。
掲示物サンプル画像




また、地震計内蔵 緊急地震速報受信機HomeSeismo(ホームサイスモ)をご購入の方には、「学校向け運用マニュアル」「病院向け運用マニュアル」のご提供をしております。